ドイツでは「ドイツらしい風景の中に暮らすことが、ドイツ人としての独自性を保つことだ」との考え方が根底にあるという。そのために、ドイツでは土地の資源を表す生態学を基礎にして国土の土地利用計画を決める一方で、計画を具体化するための伝統的、経済的技術、経済的技術を守るマイスター(職人)制度が確立されている。昔ながらの、自然や文化を現代に継承する仕組みが確立されているのである。時代が移り、科学が進歩しても、森や屋敷林、果樹園や畑や牧場と建物が一体となった風景の中で、ドイツ人としての誇りを持って生活しているのである。それは、「動植物は風土の産物なり」という真理に合致する。
それでは、日本の風景は今どうなっているのだろうか。

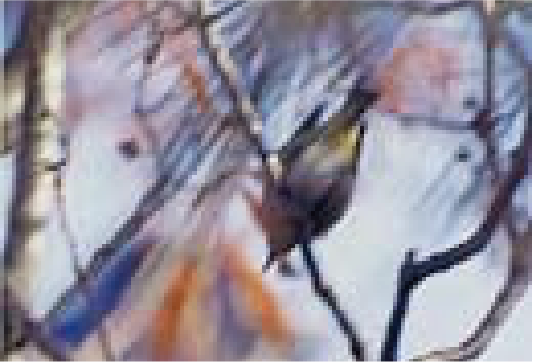

学生時代から社会に出て数年間は毎年良く旅をした。鈍行を利用して、山里の鄙びた宿に泊まって山歩きをする。金がなくて暇のある私にとって最も楽しい過ごし方だった。
その楽しさは上野駅の夜汽車に座ったときから始まり、また元の上野駅に戻ってくるまでのすべての道中にあった。まず、列車に乗り込むさまざまな出で立ちや方言を喋る人たちとの出会い。車窓から見る都会から田園、山岳部への移り変わり。地域の特色を詰め合わせた駅弁。その土地の素材で作られた簡潔明瞭な駅舎。適度に人の手が加えられた里山の自然。それらの情景は五感を通して一つ一つの画像として焼きつき、それが一遍の映画のように連続して、終着の上野駅で幕をおろす。
今も私は仕事で地方に行く機会が多い。かつて私が旅した同じルートを通ることもある。ところが車窓から見えるのは、かつての地域の特色を誇る集落に好き勝手な色や形の建物が建ちならび、田畑は放棄されたり、埋め立てられてあばた模様である。駅弁も全国ネットの単一味。どこの駅舎も皆同じ様な素材で似通った大仰なデザイン。鄙びた山里を通る道路にも「沿道美化」と称してその土地とは縁もゆかりもない外来の街路樹が一律に並び、サルビアやマリーゴールドなどの草花の帯がスミレやタンポポの草縁の中を切り傷のように伸びる。この国籍不明の風景にはカメラを向ける気にもなれぬ。せめてもと地酒をあおり、うとうとしながら上野駅に着くまでの退屈を紛らす。


子供の頃から日常的に馴れ親しんできた身近な生活の風景は、全国各地の校歌や童謡・唱歌にも表されてきた。今やそのような「繊細な自然のなかに節度を持って作られてきた日本特有の生活の風景」は破滅の瀬戸際である。「アカトンボ群れる夕焼けの原っぱや水辺」「ドジョウッコやフナッコのいる溜池」「メダカの学校のある小川」「卯の花の匂う垣根」「サクラ貝や浜千鳥のいる砂浜」「サクラの咲く隅田川の土手」「ドングリコロコロの雑木林」「虫の合唱する秋の草原」「チョウチョの飛び交うレンゲやナノハナの田や畑」などなど。
これらの風景の喪失の原因は、地域単位の自然を基盤にして成り立っていた農、林、水産業が、主として流通システムの変化により経済的に破綻したことによる。しかし一方で「自然と共生」しながら、食料自給率を低下させずに環境を維持していく土地利用の重要性が今、世界的に認識され始めている。
人間は、他の生物と同様に数千万年もの昔から自然の恵みを受けて栄えてきた。人と自然とのかかわりは地域ごとに異なるが、健全な自然、多様な自然が人間の心を癒すのは「人と自然との共生の歴史」が人間の本能にすり込んだ感覚である。日本の風土を生かした水田、雑木林、水路や溜池などの風景が万人に好まれる道理である。
このことは連続した緊張を強いられる都会に生活する人々が、休日ごとに自然が減少、単調化した都会から豊かな自然が残っている地方へと繰り出し、精神的な疲れを癒す行為に現れている。
「人も含めた生物が、空間で生き生きと活動している風景」常に「健全な生命体の営みが感じられる風景」をつくることをめざす。花や緑が単に美しいだけではテレビの静止画像を見ているのと同じである。
その風景はそこにかかわる人々にとって「心のなごむ情景」であることを心がける。単に見栄えのよい風景ではなく、その土地の文化を受け継いだ「心に感ずる風景」を。
しかし、戦後から40年以上を効率優先で突き進んできた日本の現状では、まだまだ「歴史、文化的な物や風景の保持」や「時間をかけ、手をかけながら継続的に維持していく半自然の杜や林」などの価値を認め、その存在を許容する社会的な背景が希薄である。欧米では当然のこととして進められている大火に対する防備線と、環境保全の両面から、街路、公園、緑地のオープンスペースによって都市を取り込むという発想から成り立っている「パークシステム」や「ビオトープ計画」など、「自然との共生をめざした土地利用計画や土地管理のシステム」が確立されていない。これから日々に喪失していく文化的・自然的な風景をどこまで守り、それを活かしきれるのか。また、一方で次世代に誇れる新たな風景をつくり出すことができるのか。問題は山積みである。
これからも都会及び周辺の自然環境は今よりも良くなっていることは考えにくい。そんななかで暮らす子供たちのストレスが少しでも少なくなるようなランドスケープの具体を一つずつ積み重ねていくしかないと私は思っている。今までも、そしてこれからも。
大学卒業後、造園の仕事にかかわってから今年(2002年)の8月で丸39年を経過した。その間、施工会社に籍をおいた期間も含めて、造園についての考え方の基本を変えることなく、今日まで仕事を継続してくることができた。この仕事は、絵画や陶芸などと違って、個人の力で成し得るものではない。社員はもちろんのこと、社外の個人や組織、生産や施工にかかわる人たちとの協働が不可欠である。また、「森づくり」や「自然の回復」などのプロジェクトでは、その成否は長い時間の経過を待たないと判別できない。長い期間の中で、何十、何百、と手がけさせてもらったプロジェクトの結果が今、少しずつ見え始めてきた。そのなかには反省すべき点も多いが、思いどおりの成果を生んだものもある。その原因も多岐にわたるが、その具体が少しでも明らかになってきたのは「この仕事を同じ考え方で長く続けてきたから」に他ならない。「継続は力なり」という言葉を改めて実感する。さらにこの後に向けては、価値観を共にする人々からなる「良い人の輪を広げる」ことが目標である。
業務を通して多くの人と交流の輪を広げ、データを蓄積して次の仕事に反映させる。そんな日常の繰り返しの結果が評価されれば、それが自ずから「組織の継続」にもつながっていくのだろう。 人間にとって、日本人にとっての心の安まる環境を日常の生活のなかに広げていくことが「医者は病人を治すが、造園家は病人を生まない環境をつくる」という北村徳太郎氏の考え方の実践であると思う。


「トンボやメダカがのんびりと棲めないところには人間の安心して住みづらい」ということはいろいろ報告されている。しかし、カエルやウグイスの声が聞こえなくなり、チョウチョもあまり目にしなくなったことを、身を切られるように感じる人はごく少ない。
自然にはある限界点があり、それ以内ならば人間がほんのちょっと努力すれば蘇るという不屈さを持っているが、その限界点を超えてしまうと、どうあがこうとも二度とつくり出せない。
われわれの身も周りの生物が失われてしまった時、人間の心にどんな変化が起こるのか。今こそわれわれは「形あるものが無いものから生まれる」という大原則に深く目を凝らして身の周りの自然を見つめる必要がある。日本人が心の故郷を失ってしまわないうちに。